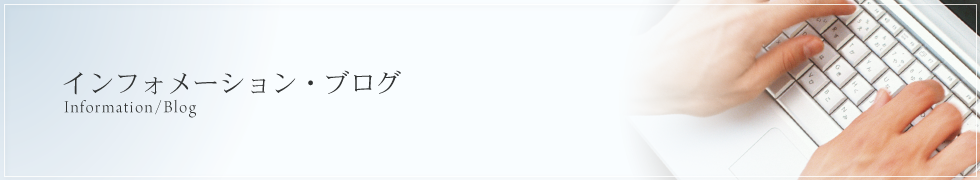超システムとしての免疫系に、老化はどのように現れるのでしようか。それを点検することは、同じ超システムである個体の老化を考えるよいモデルになります。
冬の朝、同じバス停でバスを待っている青年と老人が、同じインフルエンザウイルスにかかったとしますと、青年の方は、先ずインフルエンザにかかる確率が老人よりもはるかに低いし、かかったとしても、定型的な一次免疫反応の経過をたどって、数日のうちに治癒してしまいます。一次免疫反応と言うのは、はじめてこの抗原に出会ったときの足型的な反応です。ウイルスが細胞内に入り込み自己複製を開始すると、先ずインターフェロンの合成が始まり、ウイルスの増強を抑えようとします。マクロファージが異常を察知して、IL1などの炎症性物質を出します。IL1は発熱物質なので、熱が出、体は汗をかきます。ウイルスの粒子や蛋白はマクロファージに取り込まれ、消化された断片はクラスⅡ抗原に結合してヘルパーT細胞を剌激します。ヘルパーT細胞からは、B細胞やキラーT細胞を剌激したり、炎症を引き起こすインターロイキン群が生産されます。ウイルスが感染した細胞では、ウイルスの構造蛋白がクラス1抗原に結合して細胞の表面に提示されます。それをキラーT細胞が認識し、刺激を受ける。ウイルスを発見したB細胞も動員されるが、それはまだウイルス中和能力の低いIgM抗体を遊離するばかりです。こうして起こった免疫系の大騒動によって、インフルエンザの症状はクライマックスに達します。
しかし間もなく、B細胞はヘルパーT細胞の指令(その多くはインターロイキンの働きに帰せられる)を受けて、ようやく中和能力の高いIgG抗体を大量に分泌し始めます。IgG抗体はウイルスに直接取り付き、他の細胞への感染性などの動きを抑えてしまいます。これがウイルスの中和です。インターロイキンの影響下で、キラーT細胞はウイルス感染細胞を次々に殺して行きます。壊された細胞から飛び出したウイルスにはIgGの抗体が待ち構えて中和します。
やがて炎症はおさまり、サプレッサーT細胞が、それ以上免疫反応が過剰にならないようにヘルパーT細胞の働きを抑え、反応は終息します。青年は、再び青空の下を疾走し、病気の残骸を吹き飛ばすかのようにサッカーのボールを蹴ります。