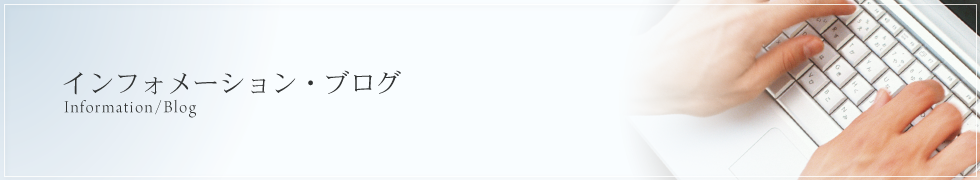老人のインフルエンザはいささか違います。それほど高い熱が出ないのに、全身がけだるい。初期の防衛反応であるインターフェロンやIL1の生産が悪く、ウイルスは広範囲に広がります。T細胞の反応もおかしく、インターロイキンのいくつかは過剰に作られるが、あるものはあまり作られない。そのために片寄った炎症が肺などに現れ、通常は問題にならないような細菌が増殖して肺炎を起こしたりします。B細胞は、ウイルスを中和できるような抗体をあまり作らない。病気は長引き、肺炎などの二次的な合併症を起こすように成り、時には致命的です。インフルエンザが治ったとしても、血液中のガンマグロブリンの濃度は異常に高く、炎症性のインターロイキンもなかなか消失しません。時にはひそんでいた免疫異常、例えば自己組織を破壊するような抗体による障害が、風邪を契機に出現することもあります。
あれほどの予備能力を持ったしなやかな免疫系に、老化とともに何が起こったのでしようか。胸腺という臓器について昔から知られていたことは、人間でも10歲代を最高にして胸腺が急速に縮小して行くことです。病気で死亡した成人の解剖報告では、胸腺は脂肪に置き換えられて非常に小さく、大きいのは急死した若者の場合だけで、そのため胸腺が大きいのはよくない体質であろうとされました。胸腺に対する関心はせいぜいそんなところだったのです。
ごく最近のユーゴスラビアの再測定の結果では、胸腺1gあたりのリンパ球の数は、生後間もない時期が最も多く10億個以上で、40歳代ではその1/100の1,000万個に過ぎません。胸腺の重量がそのころは1/10以下になっているから、40歳代の人の胸腺にいるリンパ球の総数は、小児の1/1,000以下になっているわけです。ということは、胸腺で教育されて末端の現場に送られるT細胞の数も1/1,000に減少していることに.なります。胸腺の退縮はますます進行し、70歳~80歳代になるとほとんどが脂肪に起き換わって、痕蹄程度となります。決して消失することはなく、リンパ球を作り出しています。