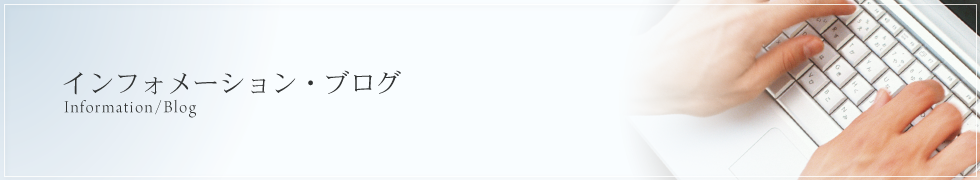T細胞は、受容体としてT細胞抗原受容体(TcR)という分子を利用し、B細胞は抗体あるいは免疫グロブリン(Ig)と呼ばれるタンパク質を使っている。いずれも「自己」以外のすべてに個別的に対応するために、億単位の異なった構造を持った受容体タンパク質である。しかし、人間のゲノムの中で、タンパク質を指定できるような遺伝子の数は、多く見積もっても十万個程度である。どのようにして遺伝子の数よりも多い受容体タンパク質を作ることができるのか。この問題を解決したのが利根川進である。
彼の発見は、科学的にも特筆すべき重要なものだったが、思想的に見ても極めて重大な問題提起となった。人間の体は60兆個の細胞でできている。形は違っているが、どの細胞も、もともとは1個の受精卵が分裂し増殖し分化することによってできたものだから、その中に収まっているDNAは、受精卵の中にあったものがそのまま複製されて受け継がれているはずである。実際、肝臓の細胞でも眼の細胞でも、含まれているDNAの構成は受精卵のそれと全く同じである。ところが抗体を作るB細胞では、受精卵や他の体細胞では離れた場所にあった遺伝子の断片がつながり合って、受精卵にはなかった新しいまとまった遺伝子の単位が作り出されていることを利根川は発見した。遺伝子は不変というそれまでの常識を覆した。
しかも、この離れて存在するDNAのつなぎ換え(再構成)というやり方で、限られた数の遺伝子断片を使って、無数のバリエーションを作り出すことができることを証明した。
抗体やTcRの持っている多様な鍵穴は、一般には3種類の遺伝子断片を組み合わせることによって後天的に作り出されたものであった。これが自己多様化のやり方である。
人間の抗体の遺伝子では4種類の断片のうち、V遺伝子と呼ばれる断片が約2,000,000個、D遺伝子断片が30個、J遺伝子が6個である。その任意の組み合わせを考えるだけでも200×30×6で36,000種類になる。さらに、つなぎ換えの部位がずれたり、そこに新しい塩基が入り込んだりして、可能なバリエーションは億単位になることが分かった。それが9種類あるC遺伝子のどれかに結合して、抗体という分子を作り出すのだ。
どのV・D・Jが組合わされるのかはもともと決まっていたわけではないから、どの遣伝子が使われるかは確率論的な問題になる。ゲノムが同一である一卵性双生児でも、同じ抗原に対応する抗体で違ったV遺伝子を使っている場合も多い。こうして免疫系は、未知のいかなる鍵にでもフィットできる一揃いの鍵穴(レパートリーという)を作り出すのである。免疫系は、このようにして造物主DNAの決定から自由になり、様々な偶然を取り込みながら、個体ごとに別々のレパートリーを作り出すようになる。生命の個別性というのは、利己的遺伝子の指令で決められていたわけではなかったのだ。
ほとんど同じ理屈がT細胞にも当てはまる。T細胞には受容体が2種類ある。αβTcRとγδTcRの2セットである。その両方で、B細胞と同じような遺伝子のつなぎ換えが起こって、多様性を作り出す。その上γδTcRの遺伝子の一部は、通常三文字ずつ読まれる暗号を、一字ずつずらして読むという離れ業をして、一つの遺伝子を何通りにも利用する。同じ文章の文字をずらして三通りの別の読み方で読むとどうなるだろうか。通常はDNAのルールで禁止されているこのような冒険をしてまで、免疫系は多様性を拡げていたのである。試算された多様性の大きさは、αβTcRでは10の16乗である。γδTcRでは10の18乗である。それだけの多様性など現実には必要ないし、また実際に作られているわけでもないのだが、そこまで可能なやり方なのである。