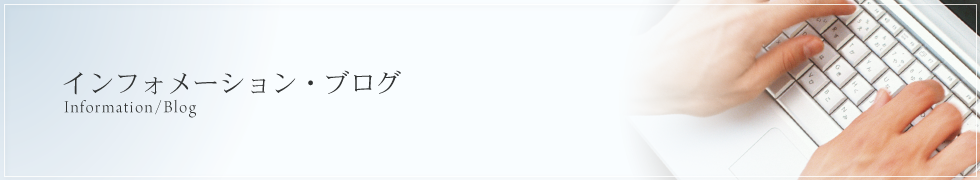元気や創造的な考えが欲しい時は現実から一歩身を引くことである。現実への適広が適正なら問題ないが、情報化社会では、ごく普通に振る舞っているつもりでも、大体が過剰適応になっている。複雑な人間関係や必要のない情報に振り回されると、自分が考え、行動するのではなく、人間社会のしがらみや時代のモ—ド、文化のコードに反応することばかりに忙しくなってしまうからである。適応が過ぎると、自我が限りなくゼロ水準に近づいていき、やがて自分が完全に消えて無くなる。
ストーカーや痴漢、万引きは、逮捕されると、口をそろえて「なぜこんなことをしたのか分からない。」という。自分が消えて無くなると、生きるためにあるべき動機が消えてしまい、このとき自己制御が出来なくなる。後に残るのは、条件反射のようなものだけである。条件反射なら、汚職、詐欺、売春、暴力に対する善悪の判断が付くはずがない。全くこの世の中は、付き合っていると、魂が擦り減ってしまう。
この魂とは、「気」といって良い。気に連なる漢字にはニーチェ的なものが少なくない。漢和辞典で拾っただけでも、気力、気合、気品、気迫、元気、正気、士気、活気、勇気、豪気、生気、精気、英気、覇気などきりがないが、この気は病気という言葉が示す通り、生の根幹に深く関わっている。ショーペンパウエルやニーチェ、ベルグソンの考えは、「生の哲学」と言われるが、日本的にいうと「気の哲学」ということになろう。
「気」については、土居健郎はこんな指摘をしている。気は、気が合う・気が付くという風にあらゆる精神活動の記述において主語として登場する。甘えの世界である日本社会で発達した気の概念には、主観的自由の意識が伴っている。
土居は、「気」が主語として登場するというのである。気が一つの生命体として意識されるのは、人は、気の存在だということであろう。事実、メロン・ボンティは「心身合一」と言った。人は体を通して世界と関わるのであれば、身に合一する心は、「気」つまり気合に外ならない。意識は、言葉を通して世界にのめり込む。これには歯止めが効かない。エピクロスは「胃袋は有限である」と言った。胃袋に限度以上のものを詰め込むと、苦痛なだけだ。
ところが言葉は限度を持たない。教師たちが「人格教育ではなく人権教育を!」と叫び、そのような教育を受けた女子高生たちが売春で補導された取り調べ室で人権侵害と叫ぶのは、言葉を食らい過ぎて胃袋がパンクしている奇怪な図の象徴であるが、それが限度というものを持たない、言葉の卑しさなのである。
だから快楽主義哲学のエピクロスは「隠れて生きよ」と言った。限度を意識しつつひっそりと生きることと、メロン・ボンディの「心身合一」は、同じことである。人は身体の可能性と限界との間を生きる。フッサールはこれを「生活世界」と言ったが、そのどれも、言葉の魔力に干渉されない霊的な内面の広がりである。ポストモダン、ポスト構造主義がここで立ち止まったのは、彼らは気というものが良く分からなかったからである。